さて、今日のお話は・・・
「習慣をデザインする5つの法則」です。
最後に、仕事やトレーニングや学習を習慣化するのに効果的な「5つの法則」を紹介します。これらはもちろん、お金を貯めることにも応用&活用できるベーシック・プリンシプル (基本原理) です。
①まず「ラップの法則」。
すでに確立している習慣に、新たに習慣にしたいことを重ね合わせてくるんでしまうという方法です。歯を磨く習慣がすでにあって確立されているなら、歯を磨くことと同時に何か新しいことをつけ足します。「歯を磨きながら、1日の流れをざっとイメージする」など。あるいは、「歯を磨きながら、アファメーションを唱える」とか・・・
毎日シャワーを浴びる習慣があって、なんの苦もなく自然にそれができているのなら、シャワーを浴びながら例えばストレッチをしてみるわけです。ストレッチの時間を別にとって新しく始めようと妙に意気込むから、なかなかできないのです。
②そして「プロット(伏線)の法則」。
小説などでは、あらかじめ物語に伏線を張っでおきます。これによって、読者は、
「あ~っ、なるほど、あのときのできごとがこれにつながったわけだ~っ!」
と、納得してあれこれ自分なりに物語をかみくだいて納得してくれるのです。これを日常生活の習慣にあてはめてみると、「早起きする」のなら、「前の夜は早く寝る」、というように、次の行動のために先回りをして何かをしこんでおくということです。
③それから「超回復の法則」。
これは、筋力トレーニングをしている方なら誰でもご存じの法則です。筋トレをするとき、重いバーベルやケーブルで負荷を加えると、その負荷によっていったん筋肉が軽く傷つきます。しかし、時間の経過とともに、その傷が修復されるときに、筋繊維が前よりもぐぐつと太くなる。これを「超回復」といいます。心も同様に、ある程度の緊張や負荷をかけてやると、強くなっていきます。場数を踏んだ役者さんが、堂々とした演技を披露するように、ビジネスパーソンもまた、緊張やストレスや失敗を乗り越えたとき、心の筋力がアップしているのです。「心の筋力を鍛える」 ことは、習慣化の過程において非常に重要なキーワードです。心の筋力がないと、中傷や非難などささいなことで心がブレて、何もかもイヤになって放り出したくなってしまうのです。
④さらに「チェックの法則」。
先ほど紹介したスーパーチェックシート(SCS)を使って、どんどん自分で自分にマルをあげていくこと。知らないうちに自己重要感がみるみる高まっていく、シンプルだけれども非常に効果がある最高の方法です。ビジネスの基本であるR-P-D-C (リサーチ⇒プラン⇒ドゥ⇒チェック)というサイクルが、水車のようにぐるぐるとうまく回り出すかどうかは、このチェック機能がきちんと働くかどうかにかかっているのです。
その意味でも、チェックシートを手帳にはさんで常に持ち歩き、こまぎれ時間を活用して、サクッとチェックする習慣をつけましょう。のラッチを注文して待っている時間や、通勤電車の待ち時間など、ちょっとしたすきま時間に、チェックする行為を流し込んでいくことで、らくらく習慣化できるものです。
⑤最後が「ステージの法則」。
先ほど「意味づけ」のところでお話ししたように、エゴからモラルヘ、モラルからメッセージへと意識のステージを上げでいくこと。自分がやっていることは、こんなにほかの人の役に立つんだという、燃えるようなワクワクの情熱を自分の仕事に対して持つことです。
ここで、有名な「旅人とレンガ職人の会話」を思い出した方も多いことでしょう。旅人が、旅の道中でレンガを積んでいる3人の職人に「何をしているんですか?」と質問をしていくお話です。
最初の職人は、「見りゃ~わかるだろう!レンガを積んでいるのさ、それにこのオレが食べていかなくちゃいけないからなあ……」とため息まじりに答えます。(エゴのステージ)
次に出会った職人は、「家族を養うために、レンガを積んでいるんだよ。それにうちの親方もカミさんも、えらく厳しくて、さぼらずにしっかりやれとガミガミうるさいしね」と、しかめっ面で返答します(モラルのステージ)。
最後に出会った職人は、目をキラキラさせて「町の人々が集う教会をつくっているんだ!これは、きっとこの町のシンボルになるはずさ」と笑顔で説明してくれます(メッセージのステージ)。
人は、自分の仕事の意味づけがしっかりできて、それが使命感(ミッション)にまで昇華されたとき、人生と習慣とが完全に一体化して、仕事をやればやるほど幸福感・至福感に満たされるという理想的な生き方ができるのです。
《まとめ》
形から入るのもOK! 習慣づけをするには、道具をそろえたり、発表の場をつくったりすることが大切。

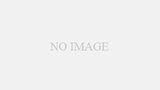
コメント